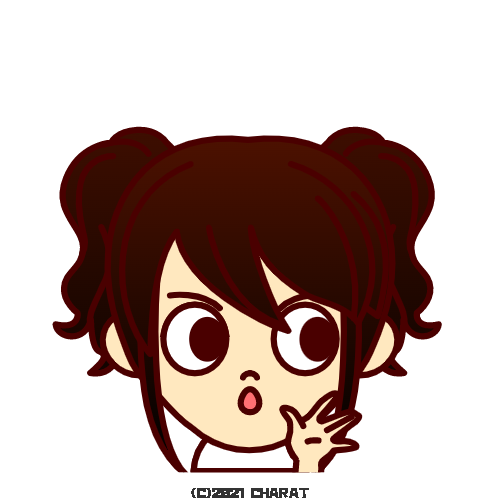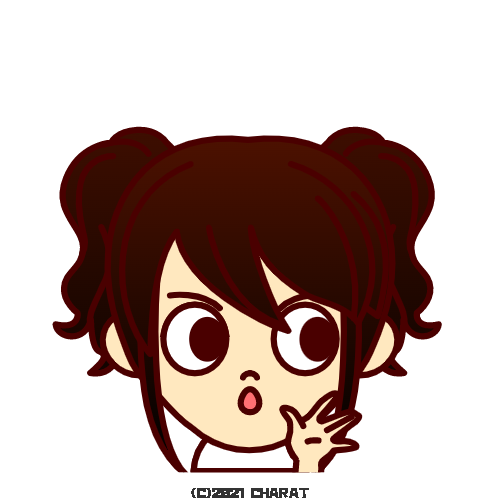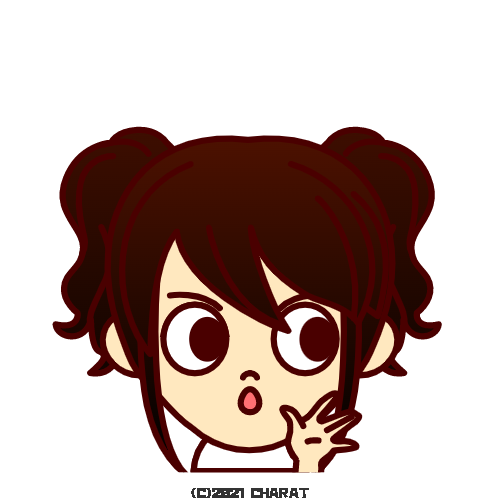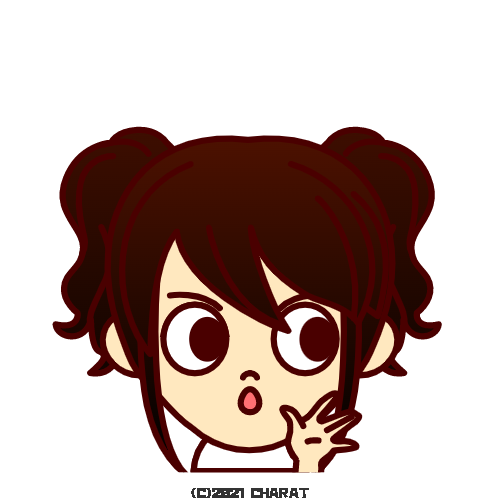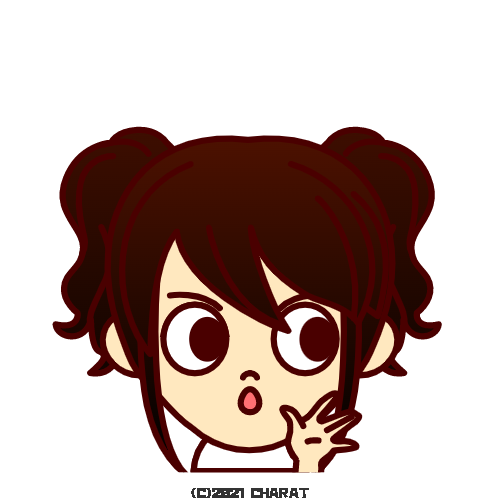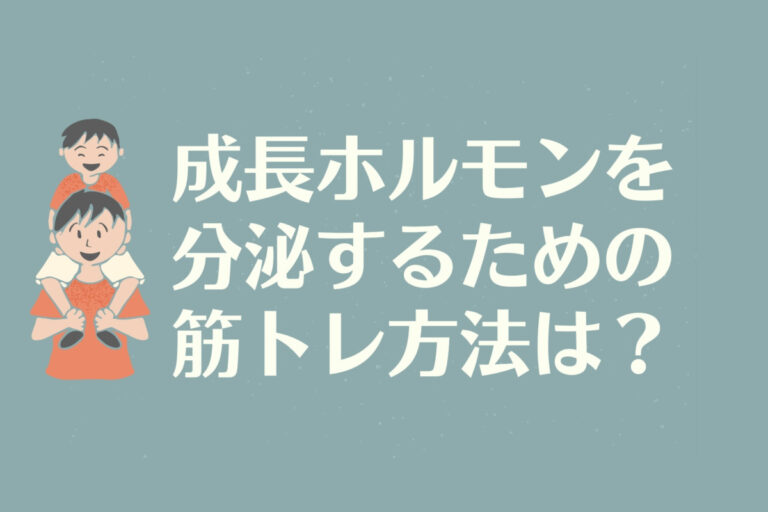背が伸びる睡眠ゴールデンタイムは?成長ホルモンを理解して深く眠る方法解説

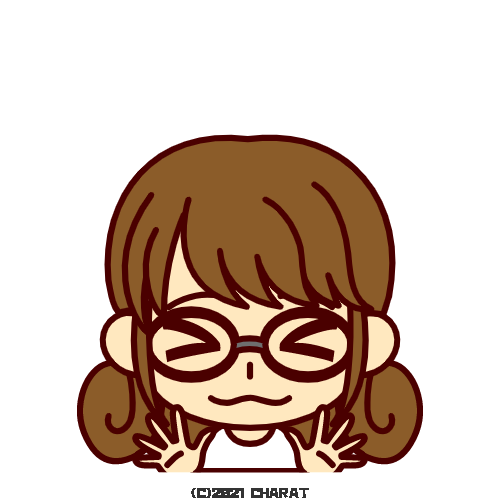
子どもの発育を考えると、睡眠不足が習慣化することは不安でしょう。
私が開発に携わっている子ども用サプリメントのユーザーヒアリングでも、質の良い睡眠を助けてくれる成分を希望する親御さんが多くおられます。
本記事では、成長期の子どもの伸長と睡眠の関係性について、以下の内容を紹介します。
|
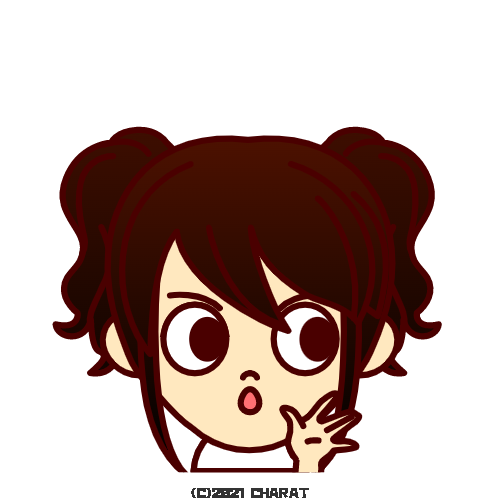
ぜひ最後までご覧ください。
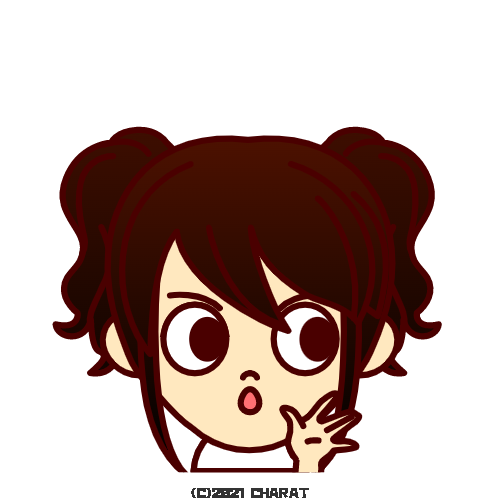
クリックできる目次
成長ホルモンが分泌される睡眠ゴールデンタイムとは?
「睡眠ゴールデンタイム」とは、入眠から3時間までの時間帯を指し、この間に成長ホルモンが盛んに分泌されます。
眠りにつくことで、成長ホルモンの分泌が開始され、入眠から3時間経過すると分泌は最大になります。
入眠から3時間を過ぎると分泌が減少し、朝にはほとんど分泌されなくなる特徴があります。
成長ホルモンは、筋肉の増強や骨の伸長、脳の疲労回復、ホルモンバランスの調整など人間の身体を支えるために欠かせません。
効率よく分泌させるためには、夜間にしっかり睡眠をとることが大切です。
と言っても、ゴールデンタイムの3時間だけでは睡眠不足になってしまいます。
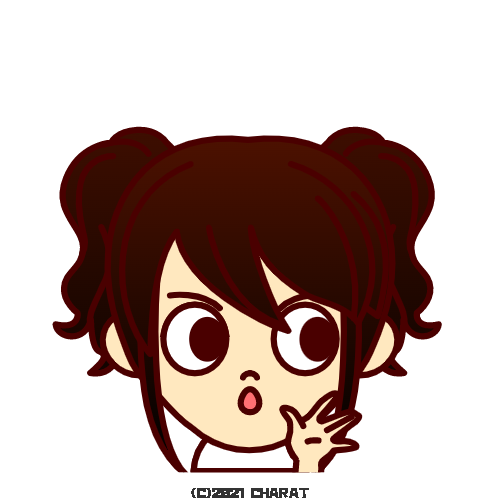
成長ホルモンの分泌が決まる睡眠リズム

人間の睡眠は浅い「レム睡眠」と深い「ノンレム睡眠」の繰り返しから成り立っています。
この間に「ノンレム睡眠」といわれる深い睡眠にスムーズに入ることができれば、成長ホルモンが分泌されます。
眠りはじめる時間帯は、成長ホルモンの分泌には関係がありません。
例えば、深夜に寝ついたとしても、眠りはじめの30〜60分に深い眠りの「ノンレム睡眠」に入ることができれば成長ホルモン分泌につながります。
一方、かつては睡眠のゴールデンタイムといわれた22時(記事内リンク)に眠ったとしても、寝入りばな30~60分の眠りが浅い場合は、十分に成長ホルモンが分泌されない可能性があります。
22時~2時の時刻説は古い
「睡眠のゴールデンタイム」で大切なことは「22時〜2時の間に眠る」ことではありません。
かつて睡眠のゴールデンタイムは、午後10時から午前2時までの時間のことを指すと言われていました。
しかし、実はこのゴールデンタイムは医学的には根拠はありません。
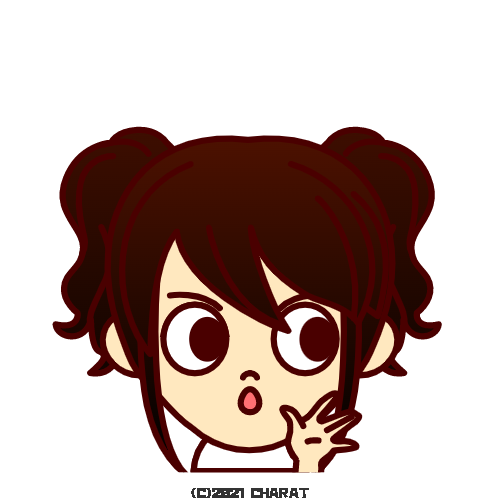
例えば、深夜1時に寝たとしても、眠り始めに深いノンレム睡眠に入れていれば、成長ホルモンは分泌されます。
しかし、22時に寝ても眠りが浅い状態ならば、成長ホルモンは分泌されにくいということです。
成長ホルモンの分泌は、時間帯ではなく、睡眠直後のノンレム睡眠と密接な関係があります。
成長期の子どもの理想的な睡眠時間は?
子どもの睡眠時間に関して、日本とアメリカで公的に示されている基準を紹介します。
文部科学省では、文教大学の教授で日本小児科学会認定小児科専門医・発達脳科学者でもある成田奈緒子氏の研究を基に、以下のように「小児期に必要な標準睡眠時間」を提案しています。
| 年齢 | 標準睡眠時間 |
|---|---|
| 5歳 | 11時間 |
| 7歳 | 10時間半 |
| 9歳 | 10時間 |
| 11歳 | 9時間半 |
| 13歳 | 9時間15分 |
| 15歳 | 8時間45分 |
| 17歳 | 8時間15分 |
文部科学省「中高生を中心とした子供の生活習慣づくりの現状と課題について」
アメリカの国立睡眠財団による子どもの睡眠時間に関する研究結果によると、理想の睡眠時間は以下の表のように年齢によって異なることが発表されています。
| 年齢 | 推奨睡眠時間 |
|---|---|
| 3〜5歳 | 10〜13時間 |
| 6〜12歳 | 9〜11時間 |
| 13〜17歳 | 8〜10時間 |
| 18〜歳 | 7〜9時間 |
【参考】アメリカ国立睡眠財団 National Sleep Foundationの睡眠時間の推奨事項
ただ、上記データはあくまでアメリカ国内での推奨であり、個人によって異なることを踏まえたうえで、ご参照ください。
学校の登校時間から逆算すると、夜更かしは健康と成長に有害であり、幸福度を損なう可能性があります。
しかし、理想的な睡眠時間を厳守するために、無理な就寝時間の固定は逆効果になる可能性があります。
あくまでも重要なのは、それぞれのライフスタイルにあった起床時間を守ることです。
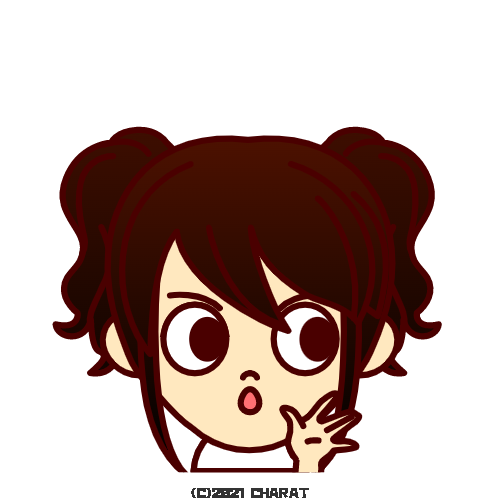
子どもが深く眠って睡眠の質を高める6つの方法
睡眠の質を高める方法を紹介します。
子どもでも実践しやすい内容を厳選しているため、ぜひ参考にしてみてください。
|
細切れ睡眠よりまとめ睡眠
細切れ睡眠よりまとめて睡眠時間を取る方が、睡眠の質を高めることができます。
細切れ睡眠は、1度の睡眠時間が短いことから睡眠不足と同じ状態に陥ってしまうからです。
まとめ睡眠を分割することで、仮眠を取りながら継続的に勉強を続けようとする子どももいることでしょう。
しかし、細切れ睡眠では、レム睡眠とノンレム睡眠のリズムが効率よく作り出されません。
それで、成長ホルモンの分泌はもちろん、記憶の定着や疲労回復の効果が弱まってしまいます。
同じ睡眠時間でも「細切れの7時間睡眠」より「まとまった7時間睡眠」の方が疲労回復効果が高く、睡眠不足を招く心配がありません。
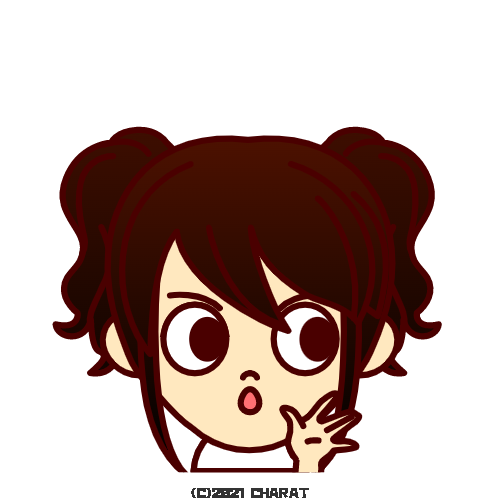
日中に適度な運動をする
適度な運動は、質の高い睡眠を作り出すための重要な要素です。
運動することで、血行が改善されて自律神経が整う効果があります。
人間が夜に眠気を感じる条件として、体温が下がることが挙げられます。
日中の運動で血行を良くして体温を上げておくことが重要です。
そうすれば、夜の入眠がスムーズに行えるようになります。
しかし、普段身体を動かす習慣がない子どもが、突然ハードな運動を始めてしまうと、関節を痛めたり挫折してしまったりする可能性もあります。
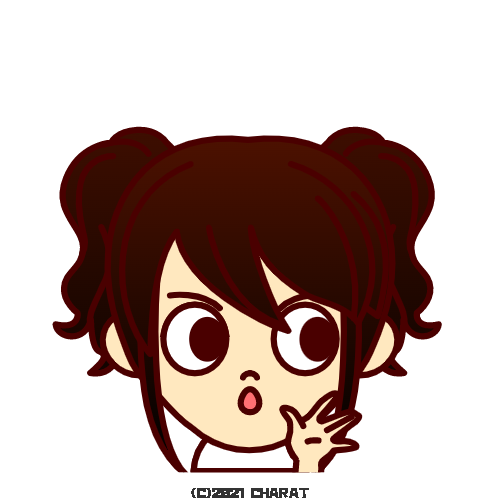
就寝3時間前までに夕食を済ませる
心地よい睡眠時間を手に入れるためにも、夕食を摂ってから眠るまでに最低3時間を空けるようにしましょう。
食事を摂ってから寝るまでの時間が短いと、人間の身体は食べ物の消化に優先してエネルギーを消費するようになるからです。
消化のためにエネルギーが供給されるため、深い睡眠に入りづらくなってしまいます。
質の良い睡眠を手に入れるためには、夕食の時間を考慮することが大切です。
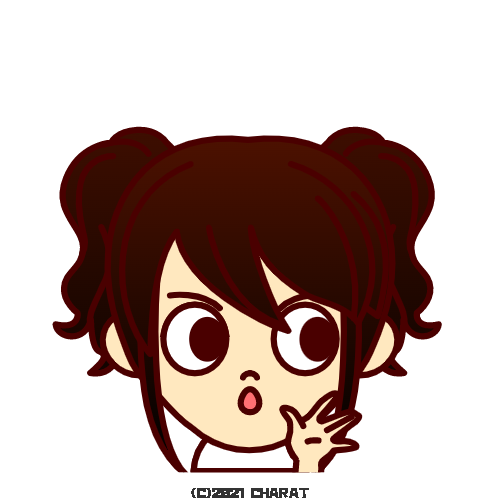
同じ時刻に寝起きする
質のいい睡眠を作り出すためには、同じ時刻に就寝・起床することが大切です。
よく「寝溜め」という言葉を耳にするかと思いますが、残念ながら人間の脳は、そこまで効率よく作られていません。
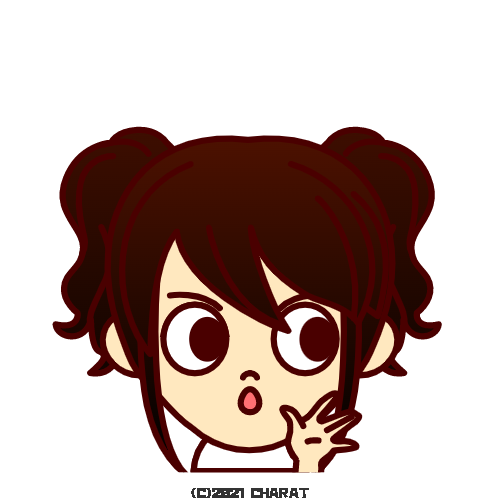
継続してしまうと、生活習慣が定まらないことで身体への疲労が蓄積され、体調不良を引き起こしてしまいます。
しかし、寝る時間と起きる時間を固定して習慣化することで、体内時計がリズム良く働くようになります。
決まった時間に自然と眠れるようになるため、しっかり1日の疲労を回復することができます。
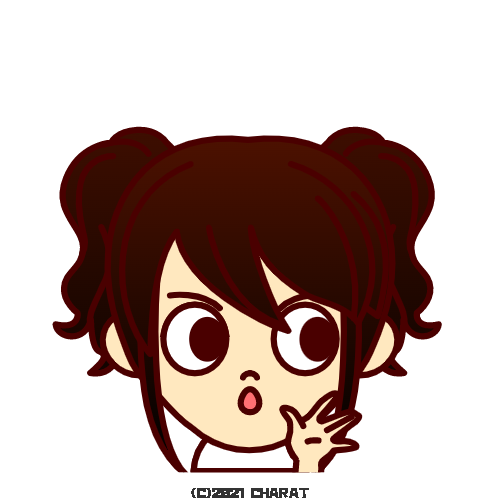
寝る直前にスマホを見ない
睡眠の質を高めるためには、寝る前にスマホやパソコン、テレビなどから距離を置きましょう。
液晶画面から発せられるブルーライトなどの強い光を浴びることで、脳が「今は昼の時間帯だ」と勘違いしてしまうからです。
睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌が抑制され、脳は興奮状態に陥ってしまいます。
「布団に入ってもすぐに寝つけず、時間だけが過ぎてしまう」経験がある方は、布団に入るまでの行動を振り返ってみましょう。
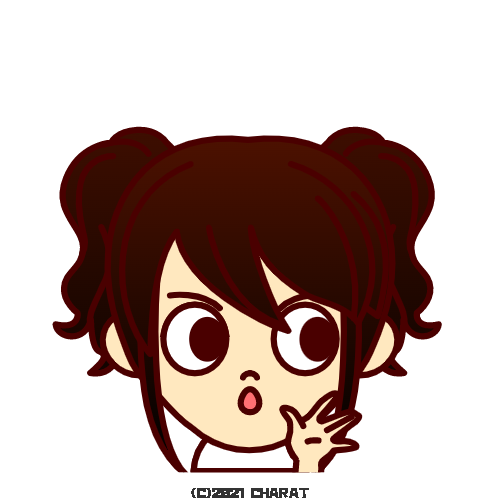
起きたら日光を浴びる
快適な睡眠時間を作り出すには、日光を浴びることも重要です。
日光を浴びることで、脳が昼間だと認識し、メラトニンを減少させます。
その結果、覚醒ホルモンであるセロトニンの分泌が優位となり、すっきりと目覚めることができます。
加えて、陽の光を浴びる行為は体内時計のリセットに繋がり、正しい睡眠サイクルを作り出すことにも役立っています。
以下を実践して、気持ちよく1日をスタートさせましょう。
|
睡眠サポートにサプリも活用できる